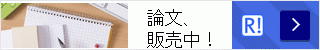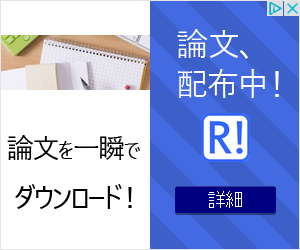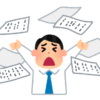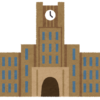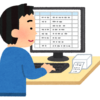卒論で文字の大きさって決められている?ルールは?
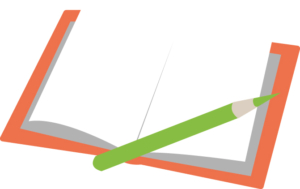
卒業論文を書く際に、「文字の大きさは自由なのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。実は、大学ごとにフォントサイズや書式のルールが決められている場合がほとんどです。文字の大きさを間違えると、提出後に修正を求められることもあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
今回は、卒論で一般的に求められる文字サイズのルールと注意点を詳しく解説します。
1. 一般的なフォントサイズのルール
大学によって多少の違いはありますが、卒論でよく採用されるフォントサイズは以下のようになっています。
| 項目 | 推奨フォントサイズ |
|---|---|
| 本文 | 10.5pt~12pt |
| 見出し(章タイトル) | 14pt~16pt |
| 見出し(節タイトル) | 12pt~14pt |
| 注釈 | 9pt~10.5pt |
| 図表のキャプション | 9pt~10.5pt |
大学の指定がない場合、本文は10.5pt~12ptが標準的です。あまり小さいと読みづらくなり、大きすぎるとページ数稼ぎとみなされる可能性があります。
2. 文字の大きさに関する大学の指示を確認しよう
卒論のフォーマットは大学ごとにルールが異なるため、まずは大学の「卒業論文ガイドライン」や「卒業論文の書き方マニュアル」を確認しましょう。
確認すべきポイント
- フォントサイズの指定(本文、見出し、注釈など)
- フォントの種類(明朝体・ゴシック体など)
- 行間や余白の設定(A4の場合、1.5行~2行が推奨されることが多い)
- 提出形式(PDFかWordか)
特に、指導教員によって細かい指定がある場合もあるので、念のため確認しておくのがベストです。
3. フォントの種類もルールがある?
文字の大きさだけでなく、フォントの種類も大学や学部ごとにルールが決められていることがあります。
よく指定されるフォント
-
日本語論文の場合
- 推奨フォント:MS明朝、ヒラギノ明朝、游明朝
- 理由:可読性が高く、アカデミックな印象を与えるため
-
英語論文の場合
- 推奨フォント:Times New Roman, Arial
- 理由:国際的に標準的なフォントとして認識されているため
基本的には「明朝体」が推奨されることが多く、「ゴシック体」は一般的な論文ではあまり使われません。
4. 文字サイズを勝手に変更するとどうなる?
卒論のフォントサイズを勝手に変えてしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
(1) 提出後に修正を求められる
大学の規定に違反していると、提出後に指摘されて再提出を求められることがあります。特に、フォーマット違反が厳しくチェックされる学部では、形式ミスが致命的になることも。
(2) ページ数を増やすための小細工と見なされる
「文字を少し大きくすればページ数が増えるのでは?」と考える人もいますが、指導教員にはすぐに見抜かれます。不自然に大きなフォントサイズは評価を下げる原因になるので注意しましょう。
(3) 可読性が悪くなる
フォントサイズを小さくしすぎると、論文が読みにくくなり、内容が伝わりにくくなる可能性があります。特に、注釈や図表のキャプションは9pt以下にすると判読しづらくなるため、適切なサイズを選びましょう。
5. 文字サイズを正しく設定する方法
卒論のフォントサイズを正しく設定するには、WordやGoogleドキュメントの「スタイル設定」を活用すると便利です。
Wordで文字サイズを統一する手順
- [ホーム] タブを開く
- [スタイル] の [標準] を選択し、フォントサイズを設定する(例:12pt)
- 見出し1、見出し2も同様に設定する(例:見出し1→14pt、見出し2→12pt)
- [スタイルの変更を保存] を選択し、全体に適用する
こうすることで、本文・見出しのフォントサイズが統一され、フォーマットミスを防ぐことができます。
6. まとめ:フォントサイズのルールを守って正しく書こう!
卒論のフォントサイズは自由ではなく、大学ごとにルールが決められている場合がほとんどです。
フォントサイズの基本ルール
- 本文は10.5pt~12ptが一般的
- 見出しは本文より大きめに(12pt~16pt)
- 注釈や図表キャプションは9pt~10.5ptが推奨される
- 大学のガイドラインを必ず確認する
文字サイズを適当に変更すると、修正を求められたり、評価が下がったりするリスクもあるため、ルールを守って適切に設定しましょう!
もし大学の指示が明確でない場合は、指導教員に相談するのがベストです。適切なフォントサイズで、読みやすく、評価の高い卒論を仕上げましょう。