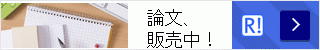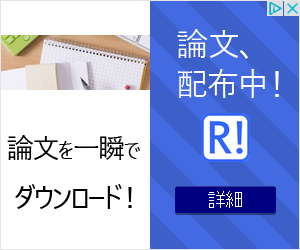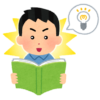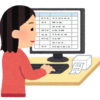卒論のページ数、どれくらいが標準的なの?
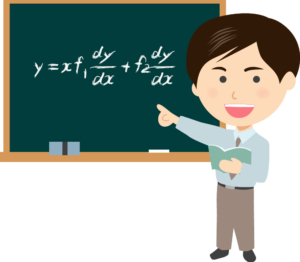
卒業論文を書くとき、「どれくらいのページ数が必要なのか?」と悩む人は多いでしょう。ページ数が少なすぎると内容が薄いと思われるし、多すぎると冗長になりがち。
実際のところ、卒論のページ数は大学や学部によって異なりますが、一般的な目安はあります。本記事では、卒論の標準的なページ数、学部ごとの違い、そして適切なページ数で仕上げるコツを解説します。
1. 卒論の標準的なページ数は?
卒論のページ数は、一般的に30~60ページが標準的とされています。これはA4サイズ、文字数に換算すると約2万~3万字程度に相当します。
学部別の卒論のページ数の目安
| 学部 | ページ数の目安(A4) | 文字数の目安 |
|---|---|---|
| 文学部・社会学部 | 40~80ページ | 3万~5万字 |
| 経済学部・経営学部 | 30~60ページ | 2万~4万字 |
| 理工学部・情報学部 | 20~50ページ | 1.5万~3万字 |
| 医学部・薬学部 | 30~60ページ | 2万~4万字 |
| 教育学部 | 30~60ページ | 2万~3万字 |
大学による違い
大学や指導教員の方針によってもページ数の基準が異なるため、卒論のフォーマットを定めたガイドラインを事前に確認しましょう。
2. ページ数が足りないとどうなる?
「ページ数が明らかに少ないと不合格になるのか?」という不安を持つ人もいるかもしれません。
(1) 最低限の基準を満たしていないとNG
大学の指定するページ数の最低ラインを満たしていないと、卒論として認められない可能性があります。
例えば、「30ページ以上」と指定されているのに20ページしかない場合、内容が不十分と判断されることが多いです。
(2) 量よりも「質」が大切
ページ数はあくまで目安であり、重要なのは「内容の充実度」です。無理にページ数を増やして水増しすると、かえって評価が下がることもあります。
3. ページ数が多すぎるのも問題?
逆に、ページ数が多すぎるのも問題になることがあります。
(1) 指定上限を超えないように
大学によっては「60ページ以内」「5万字以内」など、上限が決められていることがあります。指定を超えると、削減を求められることもあるので注意が必要です。
(2) 文章が冗長になっていないかチェック
ページ数を増やすために無駄な情報を入れると、論旨がぼやけてしまいます。
- 同じ内容を繰り返していないか?
- 関係のない話題を入れていないか?
- グラフや図表の説明が過剰ではないか?
このような点を確認し、必要に応じて削減しましょう。
4. 適切なページ数で仕上げるコツ
(1) 章立てを意識して構成を整える
卒論は一般的に以下のような構成になります。
| 章 | 内容 | ページ数の目安 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | タイトル、目次 | 1~2ページ |
| 序論 | 研究の背景・目的 | 3~5ページ |
| 本論(理論編) | 文献レビュー・先行研究 | 10~20ページ |
| 本論(実証編) | 実験・調査・分析結果 | 10~20ページ |
| 結論 | 研究のまとめ・課題 | 3~5ページ |
| 参考文献 | 使用した文献の一覧 | 3~5ページ |
章ごとのページ数の目安を意識して書くことで、適切なボリュームに仕上げることができます。
(2) グラフや図表を適切に活用する
グラフや図表を活用すると、情報が整理され、読みやすい論文になります。
ただし、ページ数稼ぎのために無意味な図を入れるのはNGです。
(3) 引用を適切に活用する
先行研究やデータを引用することで、論文の根拠が強化され、内容が充実します。
ただし、引用のしすぎには注意しましょう。自分の考察が少なくなると評価が下がる可能性があります。
(4) 文字数やフォントサイズを調整する
卒論のフォーマットには文字数・フォントサイズ・行間などの指定があるため、適切に設定しましょう。
- 行間を1.5~2行にすると可読性が向上し、ページ数が自然に増える
- 本文フォントサイズは10.5pt~12ptが一般的
5. まとめ:ページ数はバランスが大切!
卒論の標準的なページ数は30~60ページですが、学部や大学の規定によって異なります。
卒論のページ数のポイント
✅ ページ数が少なすぎると内容が薄くなり、評価が下がる
✅ 多すぎても冗長になるため、適切な範囲に収める
✅ 内容の質が重要!無理にページ数を増やすのはNG
✅ 大学のガイドラインを確認し、指定の範囲内で仕上げる
卒論は「ページ数を稼ぐこと」ではなく、「研究を的確に伝えること」が目的です。適切なページ数を意識しながら、質の高い論文を目指しましょう!