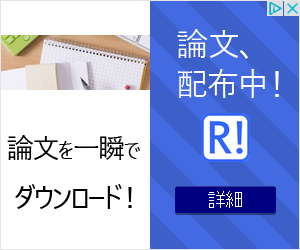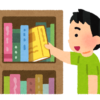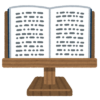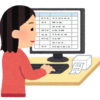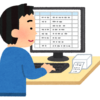卒論で先行研究があった場合、書き方の具体例は?

卒論において、先行研究は重要な役割を果たします。自分の研究がどのような学問的背景の上に成り立っているのかを示し、研究の位置づけを明確にするためです。しかし、先行研究がすでに存在している場合、それをどう取り扱うか、具体的にどのように書き進めるかについて悩む学生も多いでしょう。この記事では、卒論で先行研究を扱う際の書き方の具体例について解説します。
1. 先行研究の位置づけ
卒論を執筆する際に最初に行うべきは、先行研究がどのように自分の研究と関係するかを明確にすることです。先行研究をただ紹介するのではなく、自分の研究がどのようにそれらを引き継ぎ、発展させるのかを考えることが重要です。先行研究の位置づけを行うことで、自分の研究が学問領域の中で新たに解決しようとしている問題や、まだ十分に探求されていない点を明確にすることができます。
例えば、「〇〇の研究は、〇〇の観点から〇〇の課題を解決しようとしたが、〇〇の側面は考慮されていなかった。この点を踏まえて、本研究では〇〇に注目し、新たな視点から〇〇の解明を目指す」といった形で先行研究との対比を行い、研究の意義を示すことができます。
2. 先行研究の選定基準
先行研究を扱う際には、どの研究を取り上げるかを慎重に選定する必要があります。関連性の高い研究を取り上げることが、卒論の信頼性を高めるためには欠かせません。先行研究の選定においては、以下の点を基準にして絞り込みを行いましょう。
- 研究テーマとの関連性:自分の研究テーマとどれだけ関連が深いか。
- 学問的な影響力:その研究が学問領域においてどの程度の影響を与えているか。特に権威あるジャーナルに掲載された研究や、著名な研究者による研究は信頼性が高いです。
- 研究方法の適用範囲:先行研究で使用されている研究方法が、自分の研究にどのように適用できるか。
これらの基準に従って先行研究を選定し、その研究がどのように自分の研究に貢献するのかを示すことが求められます。
3. 先行研究の要点のまとめ方
先行研究を紹介する際には、その研究の要点を簡潔にまとめ、必要な部分だけを取り上げることが重要です。無駄に長くなることなく、要点を押さえることで、読者にとって理解しやすくなります。
例えば、以下のような構成でまとめることができます。
- 研究目的:先行研究がどのような目的で行われたのか。
- 研究方法:どのような方法を用いて研究が行われたのか。
- 研究結果:どのような結果が得られたのか。
- 研究の限界:その研究がどのような点で限界を抱えていたのか。
これらの情報を簡潔にまとめることで、先行研究の概要を効率よく伝えることができます。
4. 先行研究の批判的な分析
単に先行研究を紹介するだけではなく、その研究がどのような限界を持っていたのか、どのように自分の研究がそれを克服しようとするのかについても言及することが求められます。批判的な分析を行うことで、読者に対して自分の研究の独自性や価値を示すことができます。
批判的な分析を行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 研究方法の妥当性:先行研究で使用されている方法論が、研究目的に適していたかどうか。
- 研究結果の解釈:先行研究が得た結果をどのように解釈していたのか、その解釈に対して異なる視点があるかどうか。
- 研究の視点:先行研究が注目していない、または見落としている視点があるか。
批判的な分析を行うことで、自分の研究がどれほど新しい価値を提供するのかを強調できます。
5. 自分の研究の位置づけと先行研究の関係
先行研究を紹介した後、最も重要なのは、自分の研究がその中でどのように位置づけられるかを明確にすることです。自分の研究が先行研究に対してどのような新たな貢献をするのかを示すことが、卒論をより強固なものにします。具体的には、「本研究は〇〇を解決することを目的としており、先行研究で触れられていない〇〇の側面に焦点を当てる」などと述べることが有効です。
このように、先行研究をうまく取り扱うことで、自分の研究の価値を明確に伝えることができるのです。
卒論における先行研究の書き方は、ただの情報の羅列ではなく、自分の研究を位置づけ、学問的な貢献を示すための重要な部分です。自分の研究が先行研究にどう影響を受け、どのように新しい視点を提供するのかをしっかりと考えながら、論理的に構成することが求められます。