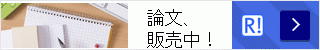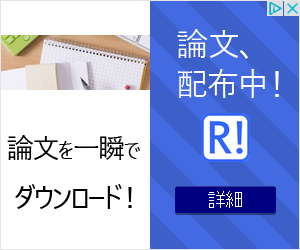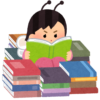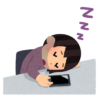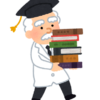卒業論文、誤字・脱字についての注意事項とは。
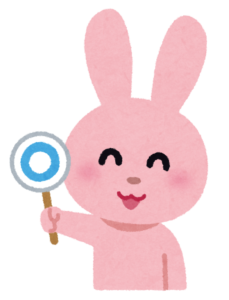
卒論は文字数が多いため、誤字脱字をチェックするのが大変ですよね。また、誤字脱字が原因で不合格になるのが心配な方も多いんじゃないでしょうか?
そこでこの記事では、卒論は誤字脱字で不合格になるのか紹介します。後半では何万文字の卒論の中から誤字脱字を簡単に見つける方法を解説しているので、ぜひご一読ください。
卒論は誤字脱字で不合格になる?
結論から言うと、卒論が誤字脱字で不合格になることはほぼありません。あまりに多すぎる場合は修正が入ることもありますが、手直しすれば合格できます。ただ、あまりに数が多いと印象は良くないので、チェックを怠ってはいけません。
誤字脱字チェックも推敲の一部に含まれるため、卒論を作る上で欠かせない工程です。できる限り丁寧に取り除き、クオリティの高い卒論を目指しましょう。
卒論の誤字脱字を対策する方法
卒論は何万文字ものボリュームがあるので、なかなか全てをチェックするのは骨が折れます。そこでここからは、誤字脱字を効率良く対策する方法を紹介します。
間違いがあると思いながら見直す
誤字脱字のチェックは意識1つで正確性が変わります。
「タイポグリセミア現象」をご存じでしょうか。文章に含まれる単語の文字を並び変えても読めてしまう現象です。
例えば、
「こんにちは みなさん おんげき ですか? わたしは げんき です。」
一つ誤字がありますが、パッと見ただけだと読めてしまいますよね。このように、ちゃんと意識して読み返さなければ見逃してしまうことがあります。
「このページには誤字脱字が必ずある」と思い込みながら読む、これだけでかなり正確性は上がるでしょう。
プリントアウトして確認する
目で読んでチェックする場合は、プリントアウトして紙面で確認するのがおすすめです。PCディスプレイと紙面では見え方が違います。特にディスプレイでスクロールしながらチェックすると読み飛ばしてしまう可能性があるのです。
卒論はページ数が多いため全てプリントするとなるとコストはかかりますが、少しでも誤字脱字を減らしたい方は試してみてください。
声に出して読む
目で読んでチェックするより正確性を上げたい場合は、声に出して読んでみるのも有効です。目で読んでいると、最初は誤字脱字を絶対に見つける意識でゆっくり丁寧に読み進めていても、知らずにうちにスピードが上がって雑になってしまうことがあります。
そこで声に出して読むと、口に合わせなければいけないため読むスピードを一定に合わせて丁寧にチェックできます。また、目で読んだだけでは気づけなかった文法ミスや読みづらい箇所なども見つけやすくなるため、卒論の完成度をさらに高めたい方にもおすすめの方法です。
他の人に読んでもらう
目で読んで声に出して読んで、それでも不安な方は他の人に読んでもらいましょう。内容を知らない人は読み飛ばしがないため、より誤字脱字に気づきやすくなります。ちなみに、同時に感想を聞くことで卒論のクオリティを上げることも可能です。
ツールを活用する
自分でチェックするのがめんどくさい方は、ツールを使った方法がおすすめです。人がチェックするより正確性は劣りますが、ある程度の誤字は自動で見つけられます。
例えばMicrosoft Wordには誤字脱字チェック機能が標準装備されています。文章を打ち込みF7キーを押すことで利用できます。
他には「Enno(https://enno.jp/)」もおすすめです。無料で使える誤字脱字チェックツールで、文章を貼り付けてチェックボダンをクリックすることで使用できます。他にも冗長表現や言葉の使い方を間違えているところも指摘してくれるので、最終チェックとして使ってみるのもいいかもしれません。
まとめ
この記事では卒論の誤字脱字について紹介しました。基本的には誤字脱字が多いからといって卒論が不合格になることはありません。ただ、万が一のことを考え、なるべくミスの無いよう見直しをしましょう。
その際におすすめなのが以下の5つです。
- 間違いがあると思いながら見直す
- プリントアウトして確認する
- 声に出して読む
- 他の人に読んでもらう
- ツールを活用する
上記の方法を使って卒論を提出する前に誤字脱字をチェックしておきましょう。